2006年12月31日 (日)
2006年私選十大ニュース
去りゆく年を振り返れば――
① ライブドア堀江貴文社長証取法容疑違反で逮捕、村上ファンド村上世彰代表インサイダー取引容疑で逮捕-1月と6月。ほんの少し前までの時代の寵児に弔辞。
② 小泉首相退陣、安倍内閣誕生-9月に戦後在任期間歴代3位(1980日)の小泉首相から安倍首相に交替。「しっかり」やってください。その前4月には送金メール問題から民主党代表交替、小沢一郎氏就任。
③ 相次ぐ知事逮捕-福島・和歌山・宮崎3県で公共工事等の発注の場面での犯罪。これとは別に岐阜県庁で12年間に17億円の裏金づくりも。
④ 教育基本法改正-強行突破、戦後教育の路線変更。戦前戦中教育への復帰でなければいいが。
⑤ 荒川静香がトリノ五輪女子フィギュアで金メダル-冬季五輪はこの金一つで閉幕。
⑥ 日銀が量的緩和政策を5年4カ月ぶり解除-7月、景気拡大が続き、先行きに自信。ゼロ金利政策が変更されても預金金利は雀の涙にもならない。
⑦ 北朝鮮が核実験実施-10月。7月にミサイルを日本海に発射したのに続く暴挙。核保有、安全保障論議の方向にインパクト。
⑧ いじめで岐阜の中2女子自殺-10月の事件だが根は深い。いじめ隠しの露見多数。
⑨ 近所の小1男児殺人で逮捕の女、水死とされていた自らの女児も殺害-秋田の片田舎での凄い事件。
⑩ WBCで王ジャパン初代世界王者に-絶体絶命の底から這い上がり、キューバ破り優勝。一方サッカーW杯は予選リーグであっさり敗退。
<次点>
・全国高校野球選手権大会で早稲田実業が初優勝。国体でも再び駒大苫小牧を下し優勝-昭和44年の松山商と三沢以来、37年ぶりの再試合で沸かせましたね。
<候補>
・東横イン二重図面で偽装工事。(数多ある企業の社会的責任無視事件の「代表」として)
・全国の高校で大学入試対策を優先、必修科目の履修漏れ多数。
・自民党、郵政民営化造反の衆院議員11人の復党を承認。
・プロ野球日本シリーズは「北海道」日本ハムが44年ぶり日本一。
年内はいろいろお世話になりました。
明年もよろしくお願いいたします。
来たるべき年が「亥」い年になりますように。
2006年11月30日 (木)
京 都 も み じ

|
| 滋賀・湖東三山の一西明寺 |
今年は京都をはさんで滋賀、奈良と欲張った。
暖かい秋だったので少し早いかなと危惧したが、トップシーズンの紅葉は裏切らなかった。
湖東三山=西明寺・金剛輪寺・百済寺は曇天だったものの、京都=東山・嵐山・長岡京光明寺は終日快晴、奈良=談山神社・室生寺・長谷寺も晴時々曇、事前の予報は良くなかったが、天候も恵まれたほうだろう。
 |
| 奈良・藤原鎌足ゆかりの談山神社 |
東山では霊鑑寺の5日間だけの特別公開をゆっくり拝観、嵯峨野の常寂光寺はこの時季は初めて、山の影が延び京の街を覆い始めていたが紅葉は堪能できた。
光明寺はライトアップの紅葉。悪くはないが、昨年のような明るい昼の方がいい。談山神社はテレビで紹介された古寺だが手入れ不足で雑然とした印象、拝観客が大勢で落着きがなかった。
こういう機会に使うはずの重い一眼レフは宿に残し、コンパクトなカメラだけで気軽に撮った。とりあえずサンプルを2枚。
2006年10月17日 (火)
東 北 8 日 間
またしばらく東北にいた。仙台に2晩泊ったあと、盛岡に行き渋民に寄って、秋田県の黒湯温泉でくつろぎ、仙台に戻って、12日に8日ぶりに帰宅した。

|
| 岩手山をバックに啄木一号碑 |
啄木生誕120年を記念した「ザ啄木展」を啄木賢治青春館、盛岡てがみ館、渋民の啄木記念館の各館で見た。それぞれ工夫を凝らした、啄木が書いたり使ったりした"本物"の多い展示だった。啄木記念館にはそれなりに入館者がいたが、他はほとんど独占の状態、ゆっくりと啄木ワールドにひたれた。
渋民は今年2度目の訪問。ようやく啄木の見た岩手山が姿を現した。この日初冠雪。一号碑のバックによく似合う。

|
| 黒湯温泉の紅葉 |
東家で握り飯をほおばりながら飽かず眺めていた。
黒湯温泉は秋田乳頭温泉郷の一番奥の一軒宿の温泉。テレビもラジオもなく(携帯ラジオを持っていくのを忘れた)、新聞も見ず(どこかに閲覧用のものはあるのかも知れないが)、携帯電話は圏外で、何度も濁り湯に浸り打たせ湯に背を叩かせ、すっかり世の中から離れたような2日間だった。ブナの黄葉が始まり、もう晩秋と言っていい秋の蒼天に山々が輝いていた。
この間盛岡では中学校の学年会があったことを、記録として付け加えておこう。
帰宅した12日は芭蕉忌。一句もなさず。ただ爆睡。
2006年10月02日 (月)
啄 木 学 会 入 会
先日国際啄木学会の理事会で入会が承認されたと通知が届いた。
前稿のとおり東京大会に出席した際、推薦者2名が必要なのだが居ない場合は空欄でも一応出してくれとの話だったので、申込書を貰っておいた。
自己紹介欄にPRを書こうにも、実績といえばこのホームページの啄木関係の雑想しかないので門前払いかと思っていたのが、まあいいかと何とか通してくれたらしい。「国際啄木学会」会員、何とも面映い。
折々雑文にお付き合い頂き、励まして(煽てて)くれた方々に感謝しなければなるまい。ご報告まで。
2006年9月16日 (金)
啄 木 学 会
丁度1週間前、会員でない者も参加自由というので、駿河台の明治大学内で開かれた国際啄木学会東京大会に出席してみた。「学会」であるから研究発表から始まるのだろうがこの日はいくつかの講演会が主で、<啄木愛好者>にも十分理解できる内容だったので、結局一日中会場にいた。
興味のある話が多く、前日やや遅かったにもかかわらず眠くもならなかった。啄木研究者・愛好者の幅は広く老若男女問わずだが、この会場には老と女が多かったように思う。
啄木生誕120年の今年は渋民を再訪したり、別途盛岡の歌碑を巡ったりしたが、この会への初参加も記念になる。こういう会も刺激になっていい。
もう一度盛岡に行く機会がある。折しも生誕120年記念の「ザ・啄木展」が盛岡の啄木・賢治青春館など4館で催されている。まだ楽しみが残っている。
2006年8月25日 (金)
在 東 北 9 日

|
| 山寺。右が奥の院如法堂 |
送り盆の日から9日間、秋田-盛岡-仙台-山形と、ちょうど暑さの厳しくなった東北にいた。
盛岡ではやはり啄木の碑等を再訪した。仙台を足場に、松島と、40年(以上)ぶりの山寺立石寺、平泉をゆっくり見てまわった。

|
| 中尊寺金色堂 |
松島は五太堂の5大明王公開など33年に一度の催しに合わせた。立石寺は「蝉の声」を聞きながら1,100余段の階段を登る。奥の院の如法堂に着いたときは汗びっしょり、ポロシャツの色が青から黒に変った。展望の開けた五大堂で吹き上げてくる涼風に生き返った。
平泉。中尊寺参詣のあと、昭和の大改修で豪華になった姿の金色堂はおそらく初めてで、じっくり拝観。高館の義経堂、当時の中心地柳之御所跡、毛越寺と歩く。 夕刻の局地的豪雨で東北線が不通になり予定していた列車に乗れなかったというアクシデントはあったが、快い疲労を感じながらの車内での缶ビールは格別であった。
◆山寺の写真をYahooPhotoのアルバムに載せました。
2006年8月15日 (火)
盆 の よ う な 月
今日月遅れのお盆。で、「月」という唱歌をふと思い出した。
♪ でたでた月が まあるいまあるい まんまるい 盆のような月が ♪
「盆のような」は、物を乗せる丸いお盆だと、恐らく二十歳の頃までは思っていた。「兎追ひし(美味し)かの山」や「負(追)はれて見たのは―」の勘違いは有名すぎるが、この件は多く丸い盆だと考えられているようである。が、お盆は丸いとは限らないでしょう。この「盆」は「盂蘭盆」のことだと思うようになったのだが。
盂蘭盆は8月15日(所謂旧暦)、必ず満月なのである。だから丸い、まあるい。明るくて父祖の霊がしばらくぶりに下界を訪れても迷うことがない。今日は旧暦7月22日、ほぼ下弦の半月なのだが残念ながら月は雲の上にある。
ついでに、七夕はなぜ7月7日か。前に「7日は月が上弦の半月で星が見やすく」と書いたが、ならば新月の方がよく見えるではないか、との疑問が出された。むかしは夜はほんとに暗い。半月の明るさは、星祭の夜人が外に出るにも、星を観るにもちょうどいい加減であったに違いない。
「渋民紀行再び」UPは少しサボっています。
2006年7月24日 (月)
渋 民 再 訪
ちょうど1週間前、昨年に続き渋民を訪れた。

|
| 渋民駅前の「雲は天才である」碑 |
昨年行けなかったり見過ごしたりした所も多くあり、気にかかっていた。渋民駅前の碑、啄木ドライブインの碑、宝徳寺の啄木の間・
白蘋の池・詩碑、啄木慰霊塔、斎藤家前の碑、等々。(実は今回もまだ見逃しているが)
梅雨の終りの時期としては薄日さえ差す暑からずの上天気なので、

|
| 啄木の「実家」宝徳寺の白蘋の池 |
渋民駅前で自転車を借りることにした。時間が少なかった割にはゆっくり廻ることができた。
啄木の住んだ旧渋民村は、今年1月10日に合併されて玉山村から盛岡市になった。一部の看板が書き換えられ以外、勿論、たたずまいは変らないが、啄木時代とまったく変らない岩手山の雄姿は今年も見えなかった。
そのうち「渋民紀行再び」としてUPしようと思っている。
2006年7月7日 (金)
七 夕
前回からひと月経った。ツキイチ雑想になった。
今日七夕。もともとは旧暦(天保暦)だから、7月7日は月が上弦の半月で星が見やすく、星祭りに相応しい時期なのだが、沖縄は別として列島はまだ梅雨のさなかである。今日もこの時季の例により晴れ間はない。旧暦では例年8月上旬(今年は7月31日)、月遅れの七夕の地に縁があるので、いつも違和感がある。
お盆もそうだ。月遅れの方が季節感に合う。
俳句なぞ勉強し始めたものだから、この「季節感」と「暦」や「節気」がずれて何とも鬱陶しく感ずる。たとえば、<七夕><お盆>は立秋過ぎのことだから秋の季語。
七夕といえば、織り姫=ベガと彦星(牽牛)=アルタイルを組合せた「ベガルタ」がJ2に降格になって3年目、今のところ昇格戦の資格をもつ3位にいる。同じ本拠の楽天はちょっと期待を持たせた時期もあったが、やはり。
などと言いつつ、今年は旧盆(月遅れ盆)には墓参りできそうもないので、なんとも風情がないが新暦盆のあたりにでも墓参しようかと思っている。
旧暦は農業の時代には生活上重い意味があったのだが、この時代、季節感と人事・行事とは、合わなくとも良しとしなければならないのだろう、言い聞かせて。
2006年6月8日 (木)
ヤマボウシ
 |
| ヤマボウシ |
近所にヤマボウシ(山法師)が植えられている通りがある。
秋にイチゴに似た赤い果実が熟れたくさん落果していることには気づいていたのだが、実は花を意識して見たのはそんなに前ではない。
街路樹としては桜が終わったあと花をつけるアメリカ花水木(アメリカヤマボウシ)をよく見かける。ヤマボウシはそれより 1ト月くらい遅れて咲きだし、今まさに満開(花ではなく「苞=ホウ」だが)。
 |
| ヤマボウシのある街路 |
怪我をした足を庇いながらゆっくり歩いていたら、昨年7月に訪れた岩手・好摩
「夜更の森」の啄木碑に寄り添うような山法師を思い出した。
丁度ドクダミの花(これも苞)が咲く時期と重なる。4枚の白色の花=苞もよく似ている。いずれも白の十字は清々しい初夏の風情を感じさせる。
追而、球状赤い実はそのまま食べられるそうである。
2006年6月05日 (水)
ひ と こ と
<ホリエモン ついでムラカミ またあちら>
真逆とは思いません、やはりそうか、と。お金は怖い。
2006年4月12日 (水)
旧 い 顔
先日学生時代のサークルの先後輩10数人が集う会があった。10年ぶりの開催だが、前回は仕事の都合で欠席したので本当に懐かしい顔が揃った。花見散策から懇親会まで、5時間もの時間も長くはなかった。
月例の職場の同期生の会にはできるだけ出席するようにしている。昨年末には近隣に在住する学校同期の仲間の会を発足させ、3か月に一度のダベリング(と昔は言っていた)を楽しんでいる。他にもいくつかそんな集いがある。
人との関係は最初に出会った時まで戻れるという。同級会が、それなりに気取った心算でも稚気・若気あふれる会になるのは、その証左だろう。
新しく人間関係を作るのはもう億劫だが、気持だけでも若返るよう幾つかの旧い顔に会えるところには極力出掛けよう。
昨秋、今春と4ヶ月の間に50年来の親しい友を失った。無常。
2006年4月3日 (月)
春 爛 漫
 |
|
千鳥が淵の桜 |
昨日雨の降り出す前に千鳥が淵に桜を観に行った。昨年の今頃はほんの咲き始めだったが、今年は満開・散り始めの樹も多い。桜に関しては21日には開花宣言と随分早い。
(東京の開花平年日は28日)
梅はかなり遅れたので、東京近辺でも梅と桜が一緒に咲いている北国の風景が見られた。
散歩に出れば、海棠、ゆきやなぎ、レンギョウ、山吹、ぼけ、パンジー、ビオラ、姫林檎、つばき、デージー、桃、みつまた、ケシ、水仙、もくれん、コブシ、野茨、なのはな、プリアンサ、庭のかぶの花、沈丁花、山吹、もちろん、さくら、等々(名を知らぬときにこう言う)百花繚乱である。カナメモチの紅もまばゆい。
近場の川(恩田川)沿いの桜が今満開のよう、また出掛けてみよう。
春爛漫とはいえ天気の変りやすい花冷えの時、お大事に。
PS:神奈川・松田町の西平畑公園の河津桜は3月半ば満開の時に再訪しました。⇒
写真
2006年3月5日 (日)
梅 未 だ し - 続
前回空振りで鬱々としていたわけではないが、また梅を見に行った。雛の日に羽根木公園と小石川後楽園に。
小石川後楽園は片隅にあるわずかな梅だがちょうど見ごろ。しかし花の遅い豊後は一輪二輪。
羽根木は26日で「まつり」は終ったがまだしばらく良さそう。これからという樹もある。
2日後の今日は春の陽の暖かい薬師池に。ここは随分遅れている。高みから見て、ん?、もう終わったのかと思うほどのさみしさ。開いているのは白梅のみで赤味のある花はつぼみのままだった。いい時期まで5日か1週間はかかる。また行くかな。
さてと、気象庁によれば、桜の開花は平年より2・3日早いというが、そうですか。細工は流々仕上げを御覧じろ、でしょうか。長期予報などはあまり信用していないのです。
うちの豊後はつぼみが赤味を帯びてきた。例年これが咲き始めて半月後に桜の開花宣言がある。
それにしても今年春の花に入れ込むのは寒冬だったせいか。ほかを考えるのがイヤになった所為か。写真は後日。
2006年2月24日 (金)
初 め て の サ ク ラ '06

|
| 松田町西平畑公園の河津桜 |
早咲きの河津桜は、本家本元の伊豆半島・河津町が勿論有名だが、神奈川・松田町の西平畑公園の「桜まつり」もなかなかなものというので、一昨22日、初めて行ってみた。
(終日晴 最高気温15℃)
この桜は普通は2月に入ると開きはじめ1ヶ月かけて満開になるという息の長い花だが、今年は寒さのため20日頃にようやく開花したという。300本あるという樹のほとんどは紅色の丸いつぼみが気を持たせるのみ。目を凝らしてようやくカメラの中に今年の「初めてのサクラ」を一枚。(今年の見ごろは3月上旬の由)
30分足らずの坂と階段、その前に寄った地酒の蔵元(中澤酒造、銘は「
松美酉」)での試飲のわずかなお酒ですっかり汗をかいた。霞で富士は見えなかったが、眼下には市街を酒匂川が悠然と流れ、ほっとする眺望だった。
木製のベンチと夕風が汗を乾かしてくれた。
2006年2月16日 (木)
梅 未 だ し
二日続いて4月中旬並みという陽気に誘われ、一昨日羽根木公園(世田谷梅が丘)、昨日薬師池公園(町田)と梅林に行ってみた。梅香を期待していたわけではないが、探りを入れる気分ではあった。
前者では数本の木が花をつけていたが、ほとんどはつぼみが赤みを帯び始めるかという段階。6日からという梅祭の看板がさびしげだった。
薬師池は郊外で気温が低いのか、たった一本若木がわずかな白い花をつけていただけで、黒褐色のままの木枝が突然の暖気の中に取り残されている感じだった。いずれも今冬の寒さを表していた。
梅の開花の遅れは寒冬の影響だが、木々は地球温暖化(高温化)という忍び寄る怪物を知ってはいない。ザレ句(川柳)をひとつ。
人まばら旗と造花の梅まつり
|
2006年2月11日 (土)
春 が 近 づ く
この寒冬も、如月も中旬に至り、三寒四温とまでは行かぬが四寒二温ぐらいになってきた。
日脚が伸び庭が少し広くなったような感じだ。日さえ出ていれば2階の部屋では暖房は要らない。
昨日、早春の静かな新宿御苑をゆっくり散策した。早咲きの水仙と福寿草はしっかり咲いていたが、梅の花は本当に一輪だけ開いていた。それでも穏やかな陽の光を受けながら春を感じてきた。
例年年明け早々開き始める鉢の紅梅が今年は2週間も遅れての開花、この頃ようやく満開になった。
「春のあしおと」が聞こえそう、春ももう少しのようだ。もっとも東京近辺はひな祭りの頃の雪というのがある。
2006年1月24日 (火)
「際」を越える
先週末母の三回忌の日、仙台はすっきりした青空の快晴、その日東京は終日雪降りの天気。 仙台では不要だった念のための雪靴が、思いがけず夜半の東京で活きた。
さて、昨夜の出来事 ――
道なき道を行く、とは開拓者の行動の謂いだが、裏街道はおろか通行不可とされていない所はすべて通行できると解釈し、跋扈、跋渉し放題。金という目的に向かって突き進む。進取の気性は買うべきだ、少しやり過ぎただけだ、とは言えない。法を<かい潜った>のではなく、法を破り、多大な被害を広範囲に撒き散らしたというのだから。検察は相当挙証の自信があるのだろう。
(有)オン・ザ・エッヂに始まるライブドアは最低限の倫理たる法の「際」(Edge)を越え、塀(これもEdge)の向こうに行った。
平均気温が最低となった12月以来の長い冬は「際」の立春まであと10日、だが冬はまだ半分残っている。おお寒い。
2006年1月1日 (日)
謹賀新年、恭賀新年、賀 正、賀 春、
頌 春、迎 春、嘉 春、壽 春‥‥ 丙戌元旦
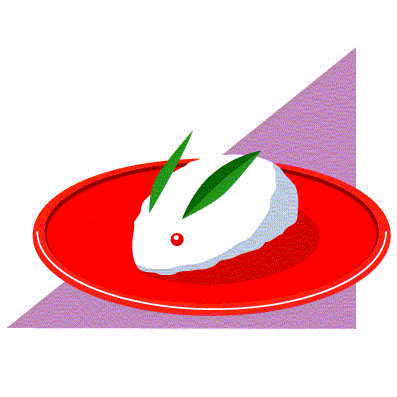 明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます
今年も相変わらずよろしくお願いいたします
2006年元旦















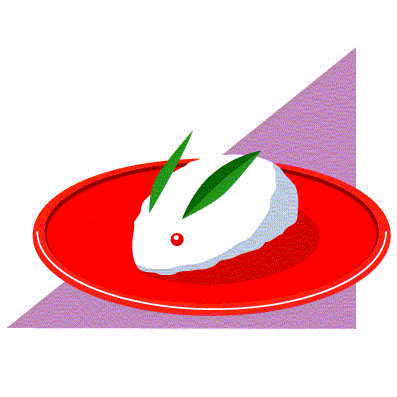 明けましておめでとうございます
明けましておめでとうございます