2007年12月19日 (水)
四 国 行
今年最後の旅行は四国だった。

|
| 徳島県祖谷渓・かずら橋 |
高松とその近辺は仕事で幾度か行ったことがあるが、他の3県は初めてである。
道後温泉から宇和島、四万十川、高知、祖谷渓
(いやけい)・かずら橋、大歩危
(おおぼけ)、金刀比羅宮と廻った。この時期としてはやや寒い感じだったが、晴か薄曇という3日間、天気にも恵まれた。
両岸の岩肌から吉野川が暴れ川たることがよく分かった。
金刀比羅宮は足の痛みを堪えながら785段を登り讃岐平野を鳥瞰、長年の望みを果たした。(足の痛みの原因はプリン体?、言わずにおこう)
バスでの移動の間、山が多いことに気づく。四国山地の南と北では気候がかなり違うことに得心がいった。
子規記念博物館や子規堂に立寄る時間がなかったのは、俳句を齧りはじめた者にとってはまことに残念であった。
 |
| 盛岡郊外鶯宿温泉の雪景色 |
この10日前には仙台、盛岡に行っていた。出発前は、上部に雪を頂いた初冬の岩手山を期待していたのだが、着いた日の盛岡は雪が降りしきっており、翌日を含め市内を廻ろうにも全く歩けないの道路状態。散策しようと時間にゆとりをもって取った切符が生きない。ただ、その分郊外の温泉への行き来の雪景色が美しかった。
そろそろ年賀状に本気で取りかからねばと思いながら、葉書の束に嘆息している。さて、と。
2007年11月30日 (金)
今年も京紅葉+近江

|
| 哲学の道・疎水分水の紅葉 |
みんな見たなぁと言いながら、今年もまた紅葉を見に京都と近江に行った。天気に恵まれいい紅葉に会えた。
日曜日(25日)の京都の駅前は大混雑、紅葉名所行きのバスは長蛇の列。
で、境内の広い所がよかろうと、吉田神社から真如堂(3度目かな)を経て金戒光明寺に。哲学の道に出て狛犬ならぬ狛ねずみ(来年の干支)の大豊神社に参り、永観堂、南禅寺とポピュラーな道を歩く。疎水分水沿いの楓はこれまでで一番鮮やかだった。

|
| 近江・永源寺の紅葉 |
この間紅葉の落葉は殆どなかった。やはり遅れていると認識。
近江はみな初めての、石山寺、三井寺、永源寺。いずれも一番良い頃合の紅葉だった。紫式部ゆかりの石山寺では写真を撮ることに気をとられ、御守を頂きながら御朱印を失念。臨済宗永源寺派の本山永源寺では、時折薄日の射す程度の空になったが、橙色のやわらかな紅葉を堪能した。
明日師走入り、京の紅葉も最後の賑わいだろうか。
そのうちスライドショーで紹介しましょう。
2007年10月26日 (金)
秋田駒ケ岳の紅葉

|
| 乳頭温泉郷黒湯温泉 |
日付を見たら前回から2ケ月も過ぎてしまった。いささか旧聞ながら、記録をかねて旅行のことでも記しておこう。
今月8~10日秋田の乳頭温泉郷黒湯温泉に行った。昨年と略同じ時期だったが、山はまだほんの一部に赤や黄色があるだけ。この夏の暑さが9月まで続いたといい、紅葉は遅れていた。
予定していた駒ケ岳の紅葉見物は、到着日は強風雨の大荒れで中止せざるを得なかった。
 |
| 秋田駒ケ岳の紅葉 |
翌々日、山頂は帽子を被ったように雲に覆われてはいたが、八合目は大丈夫かもしれないというタクシーの運転手の言葉に期待し、登ってみた。
写真の通り見ごろの山紅葉に出会うことが出来た。間もなく卒寿になる義母が初めて見る広大な山の紅葉に感激の面持ち、満足したようだった。
その帰途、宮城蔵王CCでのゴルフの翌日行った蔵王もやはり紅葉は遅れていたが、懐しい
お釜の得も言われぬエメラルド色は変らず鮮やかだった。
2007年08月27日 (月)
新暦・月遅れ・旧暦
今日は旧暦の7月15日、お盆である。空には満月がかかる。
旧盆は、日取りが毎年変るのでは都合が悪いから、8月15日の月遅れ盆ということで定着しているが、お盆は本来「旧暦盆」で、明るい月夜に先祖の御霊を迎え、送る慣わしだ。越中「おわら風の盆」は毎年9月1~3日に開催されるが、これは旧暦盆を意識した日程設定だろう。
東京では新暦盆が中心のようだが、東北はその時期は一切お盆を感じさせるものがない。寺も全く普段どおりである。
七夕はお盆の一週間ほど前(今年は8月19日)の上弦の月夜。星祭りをわざわざ梅雨の最中にやる必要もなかろうにと思うが、平塚等では早々と新暦7月7日を挟んだ日取りでやる。ご存知仙台七夕等多くは月遅れの「夏祭」だ。俳句では七夕もお盆も秋の季語。旧暦なら何の違和感もない。
明28日は全国で皆既月食が見られる。送り盆に天が素晴らしい彩りを添えてくれる。旧暦本来の霊送りの日であると思いながらこれを見る人はいかほど居られようか。
(追記:皆既月食は残念ながら厚い雲の蔭でした)
2007年08月08日 (水)
啄木の墓参り
今日ははや立秋、いささか旧聞に属するが―。
7月中旬秋田に用事があり、その前に思い立って函館に行った。盛岡から北上する新幹線は初めて、無論青函トンネルも初めて。目的は啄木の墓に参ること。今年は啄木の函館移住から丁度100年。

|
| 啄木一族の墓 |
梅雨がないという北海道の梅雨空のもと、駅に降り立ちすぐ市電で啄木一族の墓に向かう。それは立待岬に通じる道の左側の墓地にあった。手を合わせたあとしばらく矯めつ眇めつ墓碑を見ていた。隣の義弟宮崎郁雨の墓にも勿論合掌。
函館公園の碑、大森海岸啄木小公園の碑と啄木浪漫館、代用教員として勤務した弥生小学校、啄木日記等貴重な資料を所蔵する函館文学館と、啄木所縁のところを訪ね、たった1日半だったが満足して車中の人になった。
函館は40数年ぶりで地図を頼るしかなかったが、道に迷うことも無駄もなく歩くことができた。心残りは有名な函館山からの夜景が濃霧で全く見えなかったこと。
”啄木の墓浜薔薇の残り花 ”
墓碑の歌 : 東海の小島の磯の白砂に われ泣きぬれて 蟹とたはむる
函館公園の碑の歌 : 函館の青柳町こそかなしけれ 友の恋歌 矢ぐるまの花
啄木小公園の碑の歌 : 潮かをる北の浜辺の 砂山のかの浜薔薇よ 今年も咲けるや
追 記:
「函館啄木所縁」のスライドショーをアップしました。('07.09.06)
2007年07月02日 (月)
大 賀 蓮

|
| 町田市薬師池公園の大賀ハス |
薬師池公園に2,300株ほどの菖蒲田がある。昨年は6月中旬に行ったが開花が遅くまだ咲き始めの段階。今年も気になっていたのだが、ようやく昨朝、比較的涼しい曇り空だったので、梅見以来しばらくぶりに出掛けた。まともな花はほんのわずか、旬はとっくに終わっていた。
一方の大賀蓮は花期はまだ先。蓮田にはいくつかの蕾のほかは大きな葉の下に寄り添うように花芽をつけた茎があるのみだったが、開花した(特に日当りをよくして咲かせた?)ものも、二・三輪。ただ花はなくてもハスがその香りを醸していると知ったのは初めてだった。
結局は紫陽花が旬、そういう時季であった。暑い夏の朝また出直そう。
(大賀一郎東京大学農学部教授が、千葉市検見川で1951年に弥生時代の地層から2000年も前の蓮の実3個を発見、その内の1個が発芽、開花に成功。町田市円林寺、柏木氏に株分けされ、薬師池のものはそれをさらに株分けしたものという。)
2007年06月22日 (金)
梅雨入り前の旅行
殆んどホームページの更新をせず、この欄もすっかりご無沙汰してしまった。
関東などが梅雨入りした14日の雨のあと、翌日からは夏の晴天が続き、今日雨の夏至。本当は今日が梅雨入りというべきなのだろう。それはさておき、――

|
| 初夏の黒部川-トロッコ列車から |
北陸の梅雨入り直前の黒部・立山に行ってきた。黒部峡谷は晴天、立山アルペンルートは晴時々曇。立山山頂はほんの一瞬しか姿を見せなかったが、雨の気配は全くなく、またシーズンオフとあって混雑するところもなく、初夏の山岳の緑と雄大な景観をゆっくり楽しめた。
その1週間前、もちろん梅雨入り前だった盛岡に行ってきた。盛岡市内を貸し自転車で2日にわたり大分廻った。

|
| 初夏早暁の岩手山と北上川-盛岡旭橋から |
高松池畔で細い縦長の
啄木碑を発見?したが、今回は啄木関係はほどほどにして、好天の小岩井農場に半日居た。残念ながら岩手山の山頂から雲の去ることはなかったが草原に寝ころび透きとおる碧空を飽かず眺めていた。
やはりときどき遠出して気持を洗うのはいい。
(岩手山の写真はまだ雲のない早朝、盛岡北上川旭橋からのもの。)
なおふた月ほど前ですが、文字を大きく出来るよう上方にボタンをつけました。見やすい大きさにご調整ください。
2007年04月07日 (土)
盛 岡
4月からHNKラジオ深夜便の歌が変った。「ふるさとの山に向ひて」、詞は啄木の歌を4首を並べたもの(
こちらにあります)。
紅白で歌われた「千の風になって」で改めて有名になった芥川賞作家新井満(小生はよく知らなかった)が曲をつけ、自ら歌っている。よく知られる「初恋」(砂山の砂に‥‥)には及ばないかもしれないが、よく出来ているやや歌曲風の曲である。
折からNHK朝の連ドラ「どんと晴」が今週から始まった。盛岡の老舗旅館が舞台。ただし盛岡に少年時まで住んでいたがこの言葉は実は聞いたことがない。偶然に3日深夜、文化放送で「もりおか物語」という歌を聞いた。清心
(キヨミ)という若い歌手のセカンドシングルなそうだが、この歌手も勿論知らない。何となく盛岡づいている。
間もなく13日は96回啄木忌、この前後国際啄木学会春のセミナーなどが盛岡で開かれるが、都合悪しく参加できないのが残念。
しかし、知らないことが多いナ。
2007年02月22日 (木)
続 暖 冬
日本列島なべて暖冬、雪がない、タンポポが咲いた、ツバメが来た、などの春便りは枚挙に暇ない。うるさいかもしれないが、昨年は寒冬でわが家の庭の豊後梅が一輪開花したのが3月9日、今年は2月17日、20日も早い。

|
| 薬師池公園の雪吊りと梅-2/21撮影 |
昨21日1時間ほど歩いて町田市郊外の薬師池公園に行ってきた。すでに白梅が見ごろだった。昨年の2月15日はまだ黒い木肌をさらすだけだった。美しい雪吊りも冬の飾りだけのものになりそうだ。
寒さをくぐらなかったので花芽が目覚めないのではないかとも言われたソメイヨシノも早そうだ。今日の民間の予想では東京の開花が3月19日、最も早かった’02年の3月16日の記録を更新するかもしれないとの見方もある。
昨日日銀が無担保コール翌日物金利を年0.25%から年0.50%に引上げた。水準としては低いが、日本経済に春が来ているとみているということだろう。
2007年02月04日 (日)
暖 冬
今日立春。普通は「暦の上では春ですが」と言うべきところだが、この冬は暖かい日が続き、春を先取りしている。東京は未だ初雪がないそうである(我が住まう地では大寒の日に道路がまだらに濡れる程度に降ったが)。
昨年梅雨時に植え替えた鉢の紅梅が年の明けぬうちに二、三輪咲き始め、10日ほど前から満開、今盛りである。遅咲きの庭の豊後梅も蕾が膨らみ赤味を帯びてきている。春に咲くはずの椿も開き始めた。

|
| 羽根木公園の梅-2/05撮影 |
昨春はいくつかの梅の郷を見頃といわれるときに尋ねて果たせなかった。大違いである。暖かい冬は過ごしやすくていいのだが――、さて。
新聞紙上には、気象庁年平均気温の発表、IPCCの気候変動予測報告もあり、「温暖化」という言葉が目立つ。「温暖」ならいいじゃないかと言われることが心配、「高温化」と言う方が本当だろう。
周期的な変動もあるのだろうが、先々困難な事態が起こる前兆のような気もする。この問題に対する東西大国の消極的(否定的)姿勢の早急な転換が必要だろう。
寒の戻りという言葉もあるが、でもその「寒」が本来の寒さでなかった。戻ったって大したことはない。これから冬になるのかな。
2007年01月25日 (木)
初 天 神
三が日、七草、小正月、大寒など何かを書くべき節があったのに、この欄はすっかりサボってしまった。
今日は初天神。天神さんの主・菅原道真は6月誕生、大宰府左遷命令が1月、2月に逝去。いずれも25日。これから毎月25日は「天神さんの日」となった。最初の1月25日が初天神。同名の、こまっしゃくれた子供の出る落語の方が知られているかもしれない。
今や学業成就を願うこともないが(雷除の願いはあるが)、元旦、初詣に行ったものの余りに長い行列に諦めて戻ったことでもあり、今日お参りに出掛けた。鳥居をくぐった時は既に丹沢の稜線が夕茜にくっきりと浮かんでいた。神事が始まろうとしていて、それに合わせるように大鈴を鳴らした。迷惑だったかもしれない。
何か今年初めのやり残しを片付けたようないい気分で、結局はいつもの居酒屋のカウンターに座った。そして、準備ができていない明日の句会が心配になった。
2007年01月01日 (日)
明けましておめでとうございます
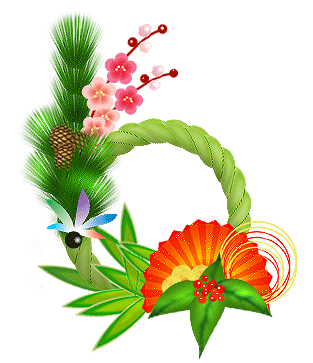 昨年中はいろいろお世話になりました。
昨年中はいろいろお世話になりました。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
新しい年が良い年になりますように祈念申し上げます。










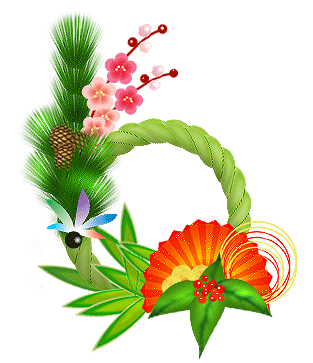 昨年中はいろいろお世話になりました。
昨年中はいろいろお世話になりました。