如雨と而酔のページ>サブノート

このページは125%程度に拡大した画面が見やすいよう設計にしています
。体 が 冷 え る
朝のコーヒーが一日の始まりという人も多いかもしれないが、寒い冬は私はまず生姜・黒糖入り紅茶から始める。
年齢の所為で血の巡りが悪くなったのか、ここ数年来手足が冷えることが多くなった。
床に入ってもなかなか足の先が温かくならない。本を読んだり、ものを書いたりして動かないで居ると冬は日中でも手が冷たくなり、指先は、痺れるとまでは言わないまでも感覚が薄れる感じになってくる。
どうやら体が常時冷えているようである。体温は普段35℃台半ばと、一般に平熱と言われている36.5℃より1℃も低い。だから風邪のときなぞは体温が37℃を超えるとゾクゾク寒気がして布団に潜らざるを得なくなる。
体温が低いのは大人の徴とあえて思おうとしてきたのだが、基本的に血行不良状態、ということをあらためて認識する。
食生活や冷房などが原因で、もともと冷え性の女性や代謝が衰える高齢者に限らず、体温の低い人は増えているという。
体が冷えると血流が悪くなり、栄養が体のすみずみにまで行き渡りにくくなるため細胞の動きが鈍くなり、抵抗力がなくなる。有害物質が溜り血管が詰まりやすくなる、必要な酵素反応が鈍くなり代謝・免疫に悪影響がでる。
運動をしたり、ゆっくり入浴したりして一日一回は体温を上げ、このような障害を除くべきという。
「風邪は万病の元」というが、漢方には「冷えは万病の元」という考え方がある。風邪は英語では Cold 、洋の東西同じかなとも思う。
で、わが対策。
まず、簡単なこと。寝るとき靴下を履く。 「寝るときに足袋や靴下を履いて寝ると親の死に目に会えない」とよく親に言われたものである。
中学まで過ごした盛岡の冬の寒さは厳しく底冷えがする。死んだ人を見るのは恐いからその方がいいと思いつつも、足袋や靴下のまま寝られないこと恨んだものである。その両親とも黄泉の国の住人となってしまったので、今は遠慮なく寝床用のゆったりした靴下を履いて床に着くことができる。
次は、冷えの大きな原因の「運動不足」を補うための毎日の散歩。
勤め人を終えた4年ほど前から意識して歩くことにした。散歩を日課とする。近所のそぞろ歩きというよりはウォーキングに近い。正式に腕を大きく振ったり腿を高く上げたりして目立つのは恥ずかしいので、やや足早(110歩/分)に5~8kmを歩くことにしている。
体調不十分でも小雨でも4km程度は歩く。筋肉は大きな熱の発生源、特に下肢を動かすことは全身の血行をよくする。歩くことの効用は他にもいっぱいあるが、すでにご存知であろう。
ゆっくり風呂に入る。 温めの風呂にゆっくり(最低10分)浸かる。血行がよくなり体温が上がる。副交感神経が優位となり、血行がよくなり気分もゆったりする。臍湯で30分がいいといわれるが、冬は寒くて無理。
もちろん食事に気をつける。
もともと和食派で、魚、野菜中心の食事で通してきており、血を汚すことが多いとされる肉類は外食のほかはすき焼き・しゃぶしゃぶ程度だから、まずはこれまでどおりで良いのだが、冷たいものはできるだけ避けるように心掛ける。
体を温める食べ物としては、根菜類、ネギ、玉ネギ、生姜、にんにく、シソ、じゃがいも、にんじん、キャベツ、鶏肉、牛肉、えび、黒砂糖などがあげられるが、にんにくと肉類以外はよく摂る。
飲み物は―。
生水が体に良いといわれ、あえて飲むよう心掛けてきたがこれを減らしもっぱらお茶(緑茶より紅茶、杜仲茶が良いというが)を飲む。ビールはさておき、冷たい飲料は避ける。飲むときは少量ずつ口に含み大事に飲む。
アルコール飲料は基本的には体を冷す働きがある。それでも日本酒やワインはその程度が低い。
利酒師・日本酒指導師範としては、当然日本酒が中心で、味・香味など比較しやすいよう常温(15℃近辺)ないし冷し酒を好んできたが、涼しい季節になるとときどき燗酒も交えるようにしている。
さて、冒頭の「生姜・黒糖入り紅茶」。
これまで紅茶は飲料としてはほとんど無視してきたが(うがい用には使う)、体を温めるのは緑茶でなく紅茶(無論緑茶には別の立派な効用がある)、そして砂糖より三温糖さらに黒糖、そして種々の薬効をもつ生姜、を知るに至って、昨冬から「生姜・黒糖入り紅茶」を愛用することになる。
作り方、というほどではないが、熱い紅茶に擂りおろし生姜と黒糖を入れるだけである。その都度おろすのは大変だから余計に作ってラップにでも包んで冷蔵庫に入れておけば2,3日はもつ。それでも面倒な人はチューブ入りのおろしなま生姜でも良し。私はもっぱらチューブにお世話になっている。
ものの本には、1日3~5杯摂ると良いというが、1回の量を多くして朝晩2回にすることが多い。 生姜は、小生も時々服用する有名な「葛根湯」などの漢方薬の原料でもあり、その体を温める作用が風邪のひき初めに良いとされ、古くから解毒・解熱・鼻づまり・鎮咳・健胃などに利用されてきたという。
他に、遠赤外線マットが大変いいというが、高価であり研究中。いまは就寝時にソフト電気あんかを太腿、腹、胸に順次乗せて、暖めているに止まっている。冷たい足を直接暖めるわけではないが、それでも血流が良くなるからか、少時あって手足まで全身温まる。
さてこれらの効果は? 体質はそう簡単に変わるものではあるまい、ゆっくり観察しよう。
-了-
('09.01.20)
タ ワ シ 摩 擦 の す す め
必要なもの : 大きい亀の子タワシ、紐付きタワシ、古歯ブラシ、1~2分の時間、やる気。
30年くらい前、仕事中震えが止まらないほどの寒気をおぼえ、ふらふらしながらようやくクルマ寄せまで辿りつき、明るいうち帰宅したことがあった。あの高熱はインフルエンザに違いない。
翌日はとても駄目。翌々日は出勤した(ように思う)。出たってどうということはないが「出る」こと自体に意義があるから、というのはお分かりだろう。
インフルエンザと所謂風邪は違うが、回復後に、風邪予防に良いと言われている乾布摩擦より強力でいいだろうと思って始めたのが「タワシ摩擦」である。
まず、大きい亀の子タワシを買いに行く。雑貨屋でこのタワシは硬いかと訊く。当方の用途を知らずに「ええ硬くて丈夫ですよ」。本当は柔らかいものが欲しいのに。そう言ったところで一種類しかないので大きな硬いタワシを求める。
紐がついて背中を擦るタワシは、それなり値がした。今は似たようなものが百円ショップでも買える。 が、安いからいいというものではない。高ければやらねばならぬという、決意が固くなる。そう買い換えるものでもない。虎の尾のような「高価な一品」には10年以上お世話になっている。
やり方は簡単である。心臓に遠いほうから近い方に擦り上げるのがいいともいうが、好きなように擦るだけである。
上半身は勿論だが、四肢は表面積が大きいのでしっかり擦る。膝の後ろなど、まことにせいせいする。尻などは表面積からいえば省略してもよい。
顔もやる。これは軽くかるく。ただ顔は古歯ブラシを使った方がよい。
各所2~3回でいいが、ほとんど往復擦るのでたくまずしてその倍は擦っていることになる。
あの大きなタワシでやるとなると尻込みする人も多いが、大きいほうが持ちやすいし効率がいい。 他人にやってもらうものではない。自分で自分の体に施すのだから耐えられないほど痛くなるようなことには絶対にならない。「いい加減」である。
最初はオソルオソルだが、だんだん自然に擦り方が強くなる。時には、タワシの粗い繊維で白い線が残ることがあるが、すぐ直る。ただその悪さをするきつい繊維は懲らしめのため切っておく。
ひと月かふた月もすれば慣れてきて、風呂場のタイル床を洗うときのような強さで擦るようになる。それでも絶対に痛くない。それはそれで「いい加減」だからである。
朝夕(夜)二度やるのがいいのだろうが、どっちか1回なら朝である。まだ覚めない起きたばかりの体がしゃんとし、すっきり清々しい気分になる。
冬は寒くて大変だろうと思われるかも知れないが、冬が一番タワシ摩擦に良い時季である。
朝起き抜けに擦ると体が温まり、一日の活動が始まるぞという気分になれる。
逆に夏が大変である。じっとしていても汗が出るときにタワシをやるとさらに暑くなるし、汗で柔らかくなった肌を擦ると傷がつきやすい。この時期はかなりサボる。
身から出たサビではないが細かなホコリが出る。タワシ摩擦後は窓を開け、これを追い出して欲しい。これが寒さ厳しい冬の最大の問題はである。だから、やはり窓を開け放つ朝がいいのである。
幼いころ田舎に行ったとき、夕方仕事を終えた馬がタワシや荒縄で体を洗ってもらうのを見て、痛かろう、可哀想に、と同情したものだ。だが、そんなことはない。一日の労働に対するお礼を施され、いい気分になっていたのだ。
効用はといえば、皮膚が鍛えられ張りが出て外気にも強くなるのは勿論だが、血行が良くなり全身の健康に役立つ、はずである。
始めてからもう30年。以来小生、風邪惹きは少なくなった。惹いても軽くて済む。
しかし風邪を惹くきっかけは、いつも乾燥期の出張や旅行である。列車とホテルの空調は乾燥度をさらに高め、咽喉が痛めつけられそこから侵入してくる。咽喉はどう鍛えたらいいのだろうか。
入念にやってもたった1、2分の健康法である。タワシ摩擦好適期のこの冬から始められては。
('04.12.25)
△TOP初 雪 ’04
――'04.12.29
平年より四日早い初雪なそうです。
朝のみぞれはすぐ雪になりそれが大きくなり、すっかり冬の姿になりました。
|
写真の上でクリックすると大きめの写真が出ます。
△TOP
と き ど き 行 く お 店
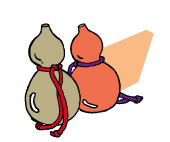 ☆ 一 瓢 (いっぴょう) ☆
☆ 一 瓢 (いっぴょう) ☆場 所 : 町田市原町田1-2-9
Tel.042-728-7673 (一時不通でしたが、大丈夫です)
2013年7月、閉店しました。
その跡に店の佇まいを残して洋風居酒屋「トラトラ」が開店しました。
電話番号もそのままです。
コの字型のカウンターに7~9人、小上がり4~5人。(奥の座敷は08年9月なくなりました)
料理はこまめに仕入れた材料を使った手作り家庭料理。焼き魚、煮魚、煮物、刺身等リーズナブルなお値段。カレイの唐揚げがいい。鯨の刺身も時々ある。
日本酒は高清水(本醸造・生貯)が主メイン。冷した浦霞の純米酒をよく飲む。越乃寒梅・久保田千寿・八海山もある。 ビールは生あり。焼酎は、いいちこ、麦千香、黒霧島、一刻者など。最近復活した「一瓢」(本銘は「酔神」「黒酔神」)がいい。ウィスキー(各種)・焼酎のボトルキープ可。ワインも置いている。
定休日は、日曜日・祝日。営業時間:17時から22時頃まで。最終23時。
地 図は
こちらにあります。
矢印のところ。小林ビル
('10.06.18改)
☆ 酒 房 い そ む ら ☆
場 所 : 港区新橋4-18-4
Tel:03-3433-3892
2012年12月、閉店しました。
その跡では日本酒ばーともいうべき「ゆくい」が営業しています。
電話番号はそのままです。
料理は旬の材料ですべて手作り、家庭料理の雰囲気のもの。お酒は各地の地酒が10種ほど。秋田・春霞、山形・上喜元、新潟・〆張鶴、栃木・四季桜、千葉・岩の井・木戸泉、石川・菊姫、島根・豊の秋、福岡・繁枡 等、いずれを飲んでも良しとするお酒。勿論、ビール(生・中瓶)、焼酎、ワインもある。
込んでいることが多いので、空席を確かめて行くのが安全。
詳しくは「いそむら」のホームページを見てください。
地 図 は
こちらにあります。
+十合ビルのところ。
('08.12.18)
※ 「とき」は、小料理・手作り料理+新潟銘酒から串焼き店に業態が変わりましたので、削除しました。('05.04.28)
要するに行きつけの店は、そのほかも含めて、今はすっかりなくなりました。
△TOP
純米酒に関するご質問への回答
而 酔
「ゲストルーム」のノートに下記のご質問がありました。ノート欄のスペースが足りませんので、ここに回答を記します。[ご質問]
お名前 : 魔酔う
日 付 : 12月11日
メッセージ : 初めまして、お酒で検索してこちらに来ました。お酒に関するページ読ませていただきました。いきなり質問で申し訳ないのですが、紙(パック?)の純米酒で980円前後で売られているお酒は余り飲まない方がよいのでしょうか? パックの場合でも千八百円以下は良くないですか。
余談ですが、昔知り合いに頂いた3リットルで千円の糖類と酸味料が入っていたパックの○ごろしはかなりぐむむな味でした。料理用には問題無く使えるのですがさすがにああいう味だと飲用では絶対買うまいと割り切れるのですが。
[回 答]
純米酒1800円~2000円は標準的な価格ではないでしょうか。紙パック詰めは同じ酒なら50~100円安いと思います。これ以下の純米酒は良くないとは言いませんが、安すぎるものは原料の質などが劣ることが多いと思います。
980円の「純米酒」はないとは言いませんが、「米だけの酒」の場合が多いと思います。これについては、「おさけ」-「お酒について知っておきたいこと」-「3.いろいろなお酒の味や香りの特徴」-「純米酒」に書いておきました。
試しに飲んでみて納得できればいいのですが、がっかりされることになりそうです。良くなかったら鍋物が多い季節ですからそちらに回せば済む話ではありますが。
「米だけの酒」でもアルコール・糖類・酸味料添加の酒よりはずっと料理用に向いています。
胃や肝臓等に苦労をかけて飲むのですから、安さだけにつられず、リーズナブルな価格帯で美味しい酒を探したいものです。普段飲る酒は、香りが料理の邪魔をすることもあり、「吟醸」が良いわけではありません。
紙パック詰めは、純米酒・本醸造酒までしかありませんが、有害な光を遮ることができ、壜に比べ流通コストが安く、従って同じ酒なら割安で、生産者、消費者双方にとってメリットがあり、私はお奨めしたい。
回答になっていないかもしれませんが。
なお、「製法品質の表示基準」が2004年1月から変わります。特に「純米酒」は精米歩合70%以下の規定がなくなりますので注意が必要です。「おさけ」をご参照下さい。('03.12.25付記)
以 上(031211)
△TOP日 本 酒 の お 勉 強
而 酔
 お酒の話は不謹慎とされるのかこの紙面では見かけなかったように思うが、付き合い始めて○○余年、あえて、酒との関わりを振り返ってみたい。
お酒の話は不謹慎とされるのかこの紙面では見かけなかったように思うが、付き合い始めて○○余年、あえて、酒との関わりを振り返ってみたい。地酒がもてはやされ始めた時期、酒どころ新潟に4年半余勤務したこともあって、数多くの地酒を試飲した(→新潟銘酒販売Webサイト)。 複数の酒を比べてその違いを知るにはできるだけ条件が同じほうが良い。お燗はでたらめに近いほどバラツキがあるので、結局「常温」で飲る。普段でも常温を好むようになった一因である。(なお常温は室温そのままではない。15℃±3℃という辺りで、夏は冷やし冬はわずかに温める。)
どうせ飲むのなら、お酒の勉強をしたいと思っていたが、なかなか機会がなく、しばらくは多くの本を読み、方々のお酒を試しながらの独習を続けてきた。
ようやく'85年、灘の大手酒造会社の1日完結の日本酒講座が初めて東京で開催されると聞いて、参加したのが体系的学習のスタートである。何となく日本酒についての一般的な知識を持った心算になった。後は意識して試すだけと、常温の酒の比較飲みを心掛けているうちに違いも分かるようになり、いい酒探しを楽しんでいた。
'97年には、日本酒通信講座を受講、原料、製造法から歴史や酒器まで系統だった勉強を、まじめにする。賞など絶えてもらったことのないが、「特別最優秀賞」という立派な名前の賞をいただく。
その秋には食事と日本酒の相性に関するスクーリングを受講、酒の種類当て、甘辛・アルコール度数の高低当ての利き酒も行なわれ、全問正解の何人かの中に入れた。
翌'98年には上級コースに進む。「日本酒指導士」資格を経て、認定試験を受験、「日本酒指導師範」となる。
その後、灘の酒造蔵に泊り込みで、蔵人(くらびと)に混じって、麹づくり・酒母(もと)づくり等一連の酒造作業をしたのも懐かしい。
これでやめればいいものを―。
15年ほど前に、一定期間酒販、料飲に従事しているお酒関係者しか受験資格がなくて諦めた「酒匠」資格を思い出す。日本酒サービス研究会・酒匠研究会連合会(SSI)という長い名前の団体がこれを引継ぎ「利酒師」の認定を行っており、われわれ日本酒愛好家も受験資格ありという。
それではと、'01年利酒師呼称資格認定試験に挑むこととした。酒類に関する一般的知識の問題はかなり自信がある。が、過去問題集にも載っていない、全く予期しなかった設問があった。
「若い15~6人のグループからミニパーティーの申込みがあった。春夏秋冬それぞれの季節ごとに、あなたが勧めたい料理とそれに合う酒の種類と提供の仕方について、理由を付して記せ。」
この問題には面食らった。
各季節4枚ずつ解答用紙がある。解答時間1時間半、焦るまいことか。ずっと飲み手でしかないので、批評はするが逆の立場では考えたことがない。40年間のいろいろな場面を思い出しながら、冷汗をかきかき何とか仕上げる。
「利酒師」にはなったが、この年齢になって他人に試されることなどもうやめようと心に決めたのであった。
さて、それでは何のための勉強か。
「居酒屋の亭主にでもなる気かね」「やっても客は来ないだろうよ」「自分でみな飲んでしまうのではないか」、と周囲は言う。勿論、居酒屋経営の才覚も体力もない。もしいうような状態になれば、生活破綻、自棄(ヤケ)酒―、やるものですか。
世の中知識があれば‘ふくらみ’が出て、幅が広くなる。楽しむための知識である。
酒について知るということは、美味しい酒が分かることであり、したがって巧まずしてお酒が旨くなり、飲むほどにゆったりした酔いの中で夢、戯れの話に世界は広がり、潤いのある人間関係をつくる。そしてまた次の旨いお酒のシーンを思い描く。これでお酒の勉強の効用は十分というものだ。肴に少々の薀蓄と。ただし、お酒の話をしながらお酒を飲むと、まず間違いなく飲み過ぎるので注意を要する。
振り返れば、アルコール・香料・調味料(甘味材料を含む)でもとの酒の量を3倍に増やす「三倍増醸酒」(略して三増酒)や「桶買い」の横行する日本酒荒廃時代に日本酒の味を知り始めたのだが、これが幸いだったのかも知れない。
20代後半の仙台勤務時代、ある大手有名銘柄の酒のまずさに驚き、東北のいくつもの酒を試しては取替え、妥協しながらもいい酒を探した。しかし、酒蔵見学の時甘味材料(セメント袋のような袋に入った蔗糖か果糖)がうず高く積まれているのを見る。まずさの原因に直面し、4年ほど日本酒を自ら飲むのはやめた(そう、会合で注がれる酒は人間関係を大事にする観点から受けた)のである。
やめることによって逆に本物を求める意欲が強くなる。いい酒があるはずとの思いから机上の勉強は続けていたので、次の'70年代前半からの地酒ブームには得たりと乗ることができたのである。また、その間に他の酒類-ウィスキー・焼酎・カクテル-の勉強もできたのも、余禄である。
いい酒を造る蔵元が増え、表示の適正化や防腐剤添加の禁止、等級制度廃止などが進んだのは、真面目な蔵元の要求もあったが、いい酒を求める飲み手の力によるところが大きい。いい飲み手が酒を良くする。
いまは、蔵元、杜氏が技を駆使し特色のある佳酒を出しており、選ぶのに苦労するほどいい酒がいっぱいある。どれもそれなりの味わいがあるとはいっても、多少知識があったほうが、自分に合ったお酒を選べるし、TPOそれぞれにいろいろなお酒を楽しめる。
日本酒に関する手引書も多い。なにか一冊読めば「通」になったような気がするだろう。自分で取っていていうのも変だが、資格などはまったく必要ない。
求めてきた酒が自分の予想したような酒だったときなど何ともうれしくなるものである。
4年ほど前の11月下旬、京の紅葉狩りの途次、以前からお参りしなければと思っていた、松尾大社に行った。この洛西総鎮守の神社は全国のお酒の神様の元締めでもあり、来るべき新年の干支・辰(龍)が朱の大杯を干さんとしている大きな絵馬が掲げられていた。奉納の100を超えようという菰冠樽に圧倒されながら神前に詣で、私の干支でもある同じ図柄の絵馬と「服酒御守」をいただく。
その御守りには、
『酒は神授の生薬。
服して心を乱さず、体を損ぜず、礼を失わず、和を破らず。
適時適量慎んで用ひざれば久しきに堪えざるべし。』
とある。さすがのご託宣である。
味や香りの感覚が衰える年代となった。しかし、美味しく飲む方法、味わって飲む作法が身についてくる年齢でもある。お酒についての「美味しく楽しく」というモットーはモットーとして、神様の教えをもう一度噛みしめて、‘久しきに堪え’るよう心がけたい。
本当の美味しいお酒は、
―― 米、 水、 麹、 酵母、 酒母。 杜氏。 酒造家の熱意。
あえて蛇足を加えれば、飲み手の酒への慈しみと味わう力。
で出来る、―――
とつけ加えておこう。
(以 上)
注:「利酒師」の‘利’は正しくは口偏に利という字。
[某紙掲載文の素原稿から]('03.08.03、10.03補)
「如 雨」 と 「而 酔」 に つ い て
1.如 雨
如雨(=じょう)は文字通り「雨の如く」「雨の如し」。水の如くであれば如水。そう黒田官兵衛孝高の異称。
使い方、下記の如し。
其従如雨(その従うは雨の如し) 賢者に従う人が多い。
如雨、言多也(雨の如く言は多なり) 言葉数が多い。
以下の3句は、いっぱい涙が落ちる、落涙のたとえ。
泣涕如雨(泣涕雨の如し)
涕零如雨(涕零雨の如し)
独宿空房 涙如雨(独り空房に宿りて涙雨の如し)
次は綺麗だ。
如雨蟲聲(雨の如き蟲聲) 秋の盛んな虫の声。
滴星如雨 雨如星(滴る星は雨の如く、雨また星の如し) 降る星は雨のように多く、雨はまた星のように美しい。
散花如雨
落葉如雨
如雨後春筍(雨後のたけのこの如し)は違う。
やや情緒的、文学的な雰囲気のある語。「啄木雑想」ページを書く。
2. 而 酔
而酔(=じすい)は読み下せば、’しこうして酔う’。「飲而酔」とすれば、’飲みて酔う’。
而は音で「じ」、酔は訓で「よう」。続ければ’じよう’。
ひっくり返して「酔うて」と読んでこれにコを付ければ「コヨーテ」。狼とは違うが、怖い肉食犬種。
「小」をつけて読めば「小而酔」=「しょうじよう」、すなわち「猩々」。猩々は中国の伝説上の人に似た大猿で、人語を解し酒好きという。オランウータンの和称。また、酒呑みを指す。大酒呑みのたとえに「五升酒の猩々」というのがある。
従って「おさけ」ページを書く。
「而酔」とつながった例は、たくさんありそうだが、WEBで検索してみても、小説の中に「不飲而酔」(飲まずして酔う)という用例があるものの、他には『隋書』東夷傳にしか見つかっていない。「靺鞨(マッカツ)」(在高麗之北)の項にある。
嚼米爲酒、飲之而酔。(米を噛み酒と為し、これを飲みて酔う)。
口噛み酒(くちかみしゅ)は最も古い酒の作り方である。今も神事に使うため醸す神社があるという。
-了-
('03.08.19)

デ カ ン シ ョ 節

| 「デカンショ節」のリクエストがありましたので、多くの替え歌がありますが、その一部を載せました。 |
| こちらのページに「正調」や替え歌をたくさん載せています。 |
△TOP
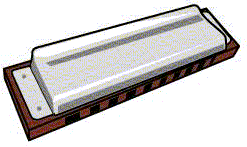
蔵 王 の 歌

| 1. | 我等歌う陸奥に奇しき山あり |
| げに山の王者 蔵王 | |
| ああ燃ゆる火を胸に抱きて | |
| ああ地に黙す此処に幾年 | |
| 熱き思いの胸に激しく | |
| 耐えてゆくもの | |
| この山に我等夢あり | |
| 2. | 我等歌う陸奥に愛しき山あり |
| 忘れじの山よ 不忘 | |
| ああ国分けて陸羽の空に | |
| ああ別れ咲くふたつの憂い | |
| 若い命の胸に激しく | |
| 深ければこそ | |
| この山に我等歌あり | |
| 3. | 我等歌う陸奥に蔵王の峰の |
| 白銀の華よ樹氷 | |
| ああ人の世の清き界とぞ | |
| ああ若人の泣きて慕いし | |
| 樹氷の山の胸に激しく | |
| 我を呼ぶもの | |
| この山に我等祈らん |
△TOP
春 の あ し お と
 「春のあしおと」は、メロディを聞くと自然に涙 がうっすらと角膜を覆います。口ずさむと何十年も前に戻ります。
「春のあしおと」は、メロディを聞くと自然に涙 がうっすらと角膜を覆います。口ずさむと何十年も前に戻ります。
|
1. 丘の陽射しは 明るくて 雑木林の楢の芽が あかく煙って伸びるから 春は ほらほら もうすぐそこまで来ているよ 2. 銀色綿毛の ねこやなぎ ゆらゆら揺れて映ってる 土蔵の影も光るから 春は ほらほら もうすぐそこまで来ているよ 3. 北風バッタリ ふきやんで とんびひょろひょろ輪を描く 田んぼのたぜりも 萌えるから 春は ほらほら もうすぐそこまで来ているよ |
こちらをクリックするとメロディが流れます。
△TOP
つ も り ち が い 十 ヶ 条
| 高いつもりで 低いのは 教養 |
| 低いつもりで 高いのが 気位 |
| 深いつもりで 浅いのは 知識 |
| 浅いつもりで 深いのが 欲望 |
| 厚いつもりで 薄いのは 人情 |
| 薄いつもりで 厚いのが 面の皮 |
| 強いつもりで 弱いのは 根性 |
| 弱いつもりで 強いのが 自我 |
| 多いつもりで 少いのは 分別 |
| 少いつもりで 多いのが 無駄 |
ついでに―、
| わらわれてわらわれて えらくなるのだよ。 |
| しかられてしかられて かしこくなるんだよ。 |
| たたかれてたたかれて つよくなるんだよ。 |
子ども叱るな来た道だ。
年寄笑うな行く道だ。
(以上は単に備忘のためのものです。)
△TOP
親 父 の 小 言
| 火は粗末にするな | 朝はきげんよくしろ | |
| 人には腹を立てるな | 風吹きには遠出するな | |
| 恩は遠くから返せ | 年寄りはいたはれ | |
| 人には馬鹿にされていろ | 子の云ふことは八九きくな | |
| 年忌法事は怠るな | 初心は忘れる勿れ | |
| 家業には精を出せ | 借りては使ふな | |
| 働いて儲けて使へ | 不吉は云ふな | |
| 人には貸してやれ | 難渋は人にはほどこせ | |
| 女房は早くもて | 義理は欠くな | |
| ばくちは打つな | 大酒は飲むな | |
| 大めしは喰ふな | 判事はきつきつく断れ | |
| 世話やきにこるな | 貧乏は苦にするな | |
| 火事は覚悟しておけ | 水は絶やさぬように | |
| 戸締りに気をつけろ | 怪我と災ひは恥と思へ | |
| 拾は届け身につけるな | 小商ものは値切るな | |
| 何事も身分相応にしろ | 産前産後大切にしろ | |
| 神仏はよく拝ませ | 病気は仰山にしろ | |
| 人の苦労は助けてやれ | 家内は笑うて封せ | |
| 大聖寺 暁仙僧上 為一家繁栄 | ||
| さればとて墓に着物は着せられず | ||
(これも単に備忘のためのものです。)
「小言」の項目や順番が気になってWebで調べましたら、江戸末期の原典が見つかったという記事がありました。こちらのファイル(『親父の小言』江戸版)に編集しました。(2013.9.14)
オリジナルは、http://d.hatena.ne.jp/fuaki/20130824/1377328362「fuakiの日記」(2013.08.24)です。
△TOP
粥 有 十 利 (しゅうゆうじり)
| 1.色 (体の色つやが良くなり) |
| 2.力 (気力を増し) |
| 3.寿 (長命となり) |
| 4.楽 (食べすぎとならず、体が安楽) |
| 5.詞清辯 (言葉が清くさわやかになり) |
| 6.宿食除 (前に食べた物が残らず胸やけもせず) |
| 7.風除 (風邪もひかず) |
| 8.飢消 (消化よく栄養となって飢えを消し) |
| 9.渇消 (のどのかわきを止め) |
| 10.大小便調適 (便通もよい) |
| 「摩訶僧祇律(まかそうぎりつ)」 |
自然災害が激しくなっている。地球温暖化のせいか
△TOPお 台 場 関 連 サ イ ト リ ン ク

画面をクリックすると大きめの写真が出ます。
「お台場」のページを開いてみる





