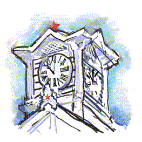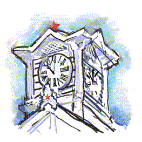
札幌滞在は明治40年9月後半のわずか半月足らずで、「一握の砂」にも3首を残すのみである。
この時期まだまだ開発途上の都市だが、いい時候でもあったからか、新しい都会‘大いなる田舎’札幌には強い印象を持ったようだ。
今でも夏の観光シーズンに続いて9月も学会などの会合で入り込み客の多い時期である。
後に「北海の三都」(函館・小樽・札幌)を書こうとして導入部だけで終わっているが、「殖民的自由の精神と新開地的
趣味」を感じている。
<しんとして幅広き街の 秋の夜の 玉蜀黍の焼くるにほひよ>
この歌から、何か懐かしい焼きコウモロコシの匂いがよみがえり、秋の札幌の街のたたずまいが見えるようだ。
札幌では、北門新報社に校正係として勤務する。紙上に「北門歌壇」を起こし、「秋風記」を掲載するなど張り切る。
この歌の歌碑が旧拓銀本店前の大通公園に歌碑(昭56.8建立)があると知って、2年半ほど前の11月に行ってはみたが、前夜から積雪ひどく歩行困難、確認出来なかったのは残念である。
<アカシヤのなみきにポプラに 秋の風 吹くがかなしと日記に残れり>
「なみき」は、‘街’と、木偏に「越」=「木越」という字を当てている。
気に入った街との別れは早かった。9月末、小国露堂
(岩手県宮古出身の新聞記者、当時札幌在住)の薦めもあり、北鳴新聞社にいた野口雨情
(後、「七つの子」「赤い靴」などで有名な童謡-だけではないが-作者)とともに小樽日報社創業に参加することを決意し、北海道第1の都市小樽に活躍の場を求め、札幌を去る。
<かなしきは小樽の町よ 歌ふことなき人人の 聲の荒さよ>
当時の小樽は流通の拠点として発展し、札幌を優に凌ぐ都市であった。進取の気性を持つ青年が活躍の場として相応しいと考えてもおかしくない。
私は最近まで、この地の歌がほとんどないとはいえ、小樽の人を貶めた感じのこの歌を碑に仕立てたのは偉いものだと思っていたが、しかし、啄木は小樽に活気を感じていて、「声の荒さ」に「真に新開地的な、真に植民地的精神の溢るる男らしい活動」
(小樽日報)を認めているのである。
尤も、戦後昭和26年小樽に初めて建てられた碑には、希望の多かったこの歌(‘小樽’の地名が入る歌はこれしかない)ではなく、<こころよく/我にはたらく仕事あれ/それを仕遂げて死なむと思ふ>が採用されている。やはり何か気に障るところがあったのだろう。
この歌の碑はそれから30年後の昭和55年、小樽駅から1.5kmほどの水天宮境内に建てられた。
(この間啄木の小樽入りとは関係なく、9月16日妻節子等は函館から啄木の次姉トラの嫁ぎ先山本氏がいる小樽に行き、寄寓する。)
<椅子をもて我を撃たむと身構へし かの友の酔ひも 今は醒めつらむ>
「小樽日報」創刊に関与、野口有情とともに3面の担当となるが、岩泉江東主筆排斥、小林寅吉事務長(後に衆議院議員)との対立等で不満が募り、必ずしも居心地のいいわけではなかった。
事務長から腕力を奮われるという物騒な事件もあり、暮も押し詰まった12月20日、
 |
| 髙橋由守氏撮影 |
生活を支える術もないのに、敢然と退社する。
そして、「門松も立てなければ、
注連飾もしない。
薩張正月らしくない」赤貧の新年を迎える。
<子を負ひて 雪の吹き入る停車場に われ見送りし妻の眉かな>
啄木が小樽日報の編集長に推薦した沢田天峰(苜宿舎同人)の口利きで、白石社長の経営する釧路新聞が拡張するのを機会に、1月19日、家族と別れがたい思いを残し、小樽を離れる。
ただし、同行予定の人が遅れて乗るべき汽車には乗れず、次の汽車を見送らずに節子は帰ったという。
厳冬、夜半の釧路に降り立った時の印象は、明かりとて乏しい、侘しさそのものだったに違いない。
<さいはての駅に下り立ち 雪あかり さびしき町にあゆみ入りにき>
釧路新聞には実質編集長格で遇され、早速、釧路新聞に「釧路詞壇」を設け、また「雲間寸間」というコラムに地方政界の裏事情を書くなど、その活躍はめざましかった。
とはいえ、生活資金は枯渇し、折角一緒に生活できるようになった家族との別れにも堪えがたく精神的にも大分疲労していた。
そして、そういうときにはつきものの、酒と女が出てくるようになる。
「生れて初めて、酒に親しむ事だけは覚えた。盃二つで赤くなつた自分が、僅か四十日の間に一人前飲める程になつた。芸者といふ者に近づいて見たのも生れて以来此釧路が初めてだ。」と日記に記す(明治41.2.29)。
<あはれかの国のはてにて 酒のみき かなしみの滓を啜るごとくに>
<小奴といひし女の やはらかき 耳朶なども忘れがたかり>
花柳界に出入りし、芸者小奴との交情を深める。笠井病院看護婦の梅川操との悶着も起こすなどほかにも女性との関わりが多くなり、後ろ指をさされたりもする。
自らの紙面に花柳界の話題「
紅筆便り」の連載も始める、といった具合である。
「兎も角も此短時日の間に釧路で自分を知らぬ人は一人もなくなった」
(前記日記)状態になり、居心地が悪くなる一方、日景安太郎主筆への不満が重なり、省みて締りのない満たされない生活に淋しさを感じ、文学への熱き思いいよいよ募り、上京する意志を固める。
<しらしらと氷かがやき 千鳥なく 釧路の海の冬の月かな>
と、小奴との寒夜の散歩を懐かしむ思い出の地、釧路を滞在76日で去る。海路、函館、小樽を経て、再び船で東京に向かう。'追はるるごとく'出た故郷を通りたくなかったからといわれる。
成算があろうはずがないが、更なる苦渋の日々が待ちうけているとも思ってはいない。
釧路には、24もの啄木の歌碑があるという(釧路観光協会ホームページ。渡部芳紀教授のホームページによれば23)。碑に刻まれた歌を巻末に記す。
15kmも離れたところにある丹頂鶴で有名な釧路湿原以外に特に観光資源とてなく、啄木を利用したいのは分かるが、滞在76日に24碑、大変な熱の入れ方である。盛岡にも多いが16程度と聞く。
(北海道結語)
北海道11ヵ月
(明治40年5月5日~41年4月21日)は、‘職’ではなく「食を求めて」
(日記) の流転、漂泊の旅となった。その後の紆余曲折の短い人生の不幸つづきの縮図のようである。希望と落魄、何かを求める人間には避け得ないことなのだろう。
第 4 回 -了-
(特に注書きのないものは「一握の砂」より)
('03.07.20)



![]() 」の「
」の「![]() 」の字はカバーされていないため、本サイトでは「啄木」と表記します。ご了承ください。
」の字はカバーされていないため、本サイトでは「啄木」と表記します。ご了承ください。