~~ 日頃よく訊かれる日本酒についての質問に答えます。 ~~
| お酒について知っておきたいこと<目次> |
|---|
5.日本酒の製造工程① ―― 工程のあらまし
日本酒の造り方のあらましを下図に示す。
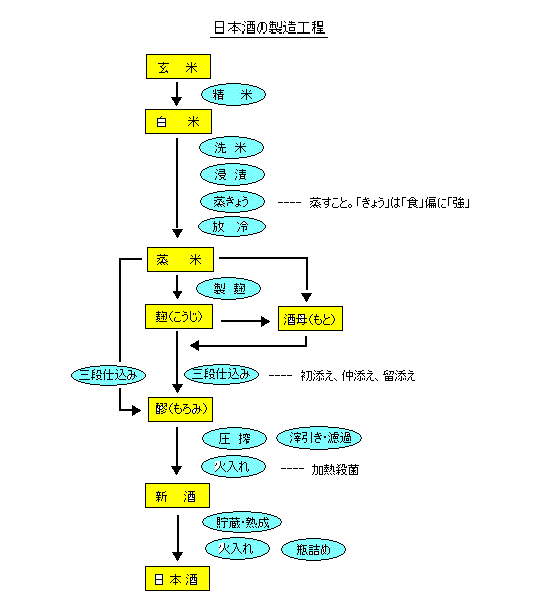
ごく簡略に製造工程を見てみよう。あくまで普通の酒造り工程である。
まず、原料となる玄米を80~70%程度まで精米し、白米(精白米)とし、米を研ぎ(洗米)、水に浸けて吸水させ(浸漬)、余分な水をとり除いた(水切り)のち、これを蒸して(蒸きょう)、蒸米とする。
蒸米の一部は麹(こうじ)づくりにまわす。
蒸米に種麹(黄麹菌)を繁殖させ麹(米麹)をつくる(製麹=せいきく)。
この麹は、酒母(もと)づくりと三段仕込みに使い、米の澱粉を糖化するはたらきをする。
一方で、蒸米に麹・水・酵母を加えて「酒母(しゅぼ、もと)」をつくる。
醪の発酵を促す酵母を大量に培養したもので、酒をつくるまさしく元になる。酵母は糖分をアルコール(と炭酸ガス)に変えるはたらきをする。
この酒母に、さらに蒸米・麹・水を3回に分けて加える「三段仕込み」を行う。初日 初添、二日目は休み(踊り)、三日目 仲添、四日目 留添という。発酵させる状態にした酒母・蒸米・麹・水の混合物が醪(もろみ)である。
20日ほどで発酵を終えた醪ができあがる。
この醪を圧搾して日本酒(新酒)を取り出す。搾りかすが酒粕である。
この酒はやや濁っているため滓(おり)引き・濾過して澄んだ酒にし、60~65℃に加熱、殺菌する(火入れ=低温殺菌)。その後一定の冷涼な温度に保ち貯蔵、熟成させる。
貯蔵した酒を調合・加水(割水)・炭素濾過を行い、火入れをして、瓶詰めなどで出荷される。
それぞれの段階でいろいろな工夫(味や香りを良くする工夫、コストを下げる工夫等)が施され、多様な日本酒ができあがる。
('04.01.12)
6.日本酒の製造工程② ――原料米、水
各製造工程の説明に入る前に、大きく酒質に関わる原料米、醸造用水などの原料について述べる。ここではまず原料米(酒米)について、ふれておきたい。
[原 料 米]
酒づくりに適した米「 酒造好適米」という語はもう知っておられるだろう。米飯にする米(食用米)に比べて粒が大きく、米の中央にある白色不透明の心白という部分が大きく、タンパク質の含有量が少ないなどの特徴がある。
山田錦や五百万石が特に有名である。
酒づくりに使われている米すべてが「酒造好適米」という訳ではない。醸造技術が進んで酒づくりに食用米が使われる場合もある。「こしひかり100%」などという表示があるものもあるのでお分かりになるだろう。
とはいえ、普通米が使われるのはコストの問題が大きい。技術で大分補えるようになったというべきだろう。 酒造好適米の使用量は普通米よりずっと少ないのである。酒造好適米の産出量は年間7万トン足らずで、とうてい酒造用の米をまかなえるはずがない。
多くの吟醸酒、大吟醸酒は、かなり「酒造好適米」を用いていると考えていいが、その「酒造好適米」にも種類とグレードがあるから、みなみな良い酒だというわけではない。
それなりの酒でも「酒造好適米」は麹作りにのみ使い、掛米(かけまい=三段仕込みに使う米)は普通米というものが多い。
参考までに、主な「酒造好適米」を上げておこう。
酒造好適米は、
①心白が大きい、②外硬内軟性に富む、③タンパク質含有量が少ない、④大粒である、
という適性を備えている酒米である。
稲穂の背丈が非常に高く、日中は気温が高く朝晩は冷える山麓や谷合いが栽培適地とされる。
各地でその土地に合った酒造用米が開発されており、近年は多くが「酒造好適米」に認定されている。
| 銘 柄 | 主な産地 | 銘 柄 | 主な産地 | 銘 柄 | 主な産地 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 山 田 錦 ① | 兵 庫 | 五百万石 ② | 新 潟 | 美 山 錦 ③ | 長 野 | ||
| 雄 町 ④ | 岡 山 | 八反錦1号 ⑥ | 広 島 | 兵庫北錦 | 兵 庫 | ||
| 兵庫夢錦 ⑤ | 兵 庫 | 華 吹 雪 ⑧ | 青 森 | 若 水 | 愛 知 |
| 他に、吟風(北海道)⑦、出羽燦々(山形)⑨、玉栄(滋賀・鳥取)⑩ などが上位にある。 |
| ※ ◯の中の数字は、酒造好適米の品種別作付面積順位(03年度)。 83品種のうち上位3品種で7割を超える。10位まででは8割5分にもなる。 |
| 銘 柄 | 主な産地 | 需要量(玄米トン) | |
|---|---|---|---|
| 山 田 錦 ① | 兵 庫 | 30,932 | |
| 五百万石 ② | 新 潟 | 16,807 | |
| 美 山 錦 ③ | 長 野 | 4,357 | |
| 秋田酒こまち④ | 秋 田 | 1,887 | |
| 雄 町 ⑤ | 岡 山 | 1,635 | |
| 八反錦1号 ⑥ | 広 島 | 1,434 | |
| 吟 風 ⑦ | 北海道 | 1,391 | |
| 出羽燦燦 ⑧ | 山 形 | 1,190 | |
| 越 淡 麗 ⑨ | 新 潟 | 1,051 | |
| ひちごこち⑩ | 長 野 | 1,049 |
この後に、花吹雪(青森)、蔵の華(宮城)、飛騨ほまれ(岐阜)、
ぎん銀河(岩手)などが続く(500トン以上)。
[酒 造 用 水]
酒づくりには、大量の水を要する。使用する米の重量の20~30倍も使うといわれる。
酒造用水は、醸造用水とビン詰め用水に分けられる。醸造用水は洗米、浸漬用水、仕込み用水、雑用用水に、更にビン詰め用水は、洗ビン用水、割水用水、雑用用水に分けられる。
こんなことはどうでもいいことだが、利酒師認定をするSSIの作ったジマンの分類なのか、認定試験にまで出る。(これをアップしたら筆者も忘れるだろう、ゴメン)
洗米、浸漬用水は読んで字の如く、米糠、その他の汚れをとり、米に水を十分に浸透させるための水。
雑用用水は、洗浄用とボイラー用水など。洗ビン用水も読んで字の如し。
割水用水は、ビン詰の時原酒に加えてアルコール濃度を調整するための水。
― というわけで、それなりに大事な水だが、問題は仕込み用水である。

('04.01.12)
|
| お酒について知っておきたいこと |
|---|
|
このページのトップに戻る
前のページに戻る
「おさけ」トップに戻る |